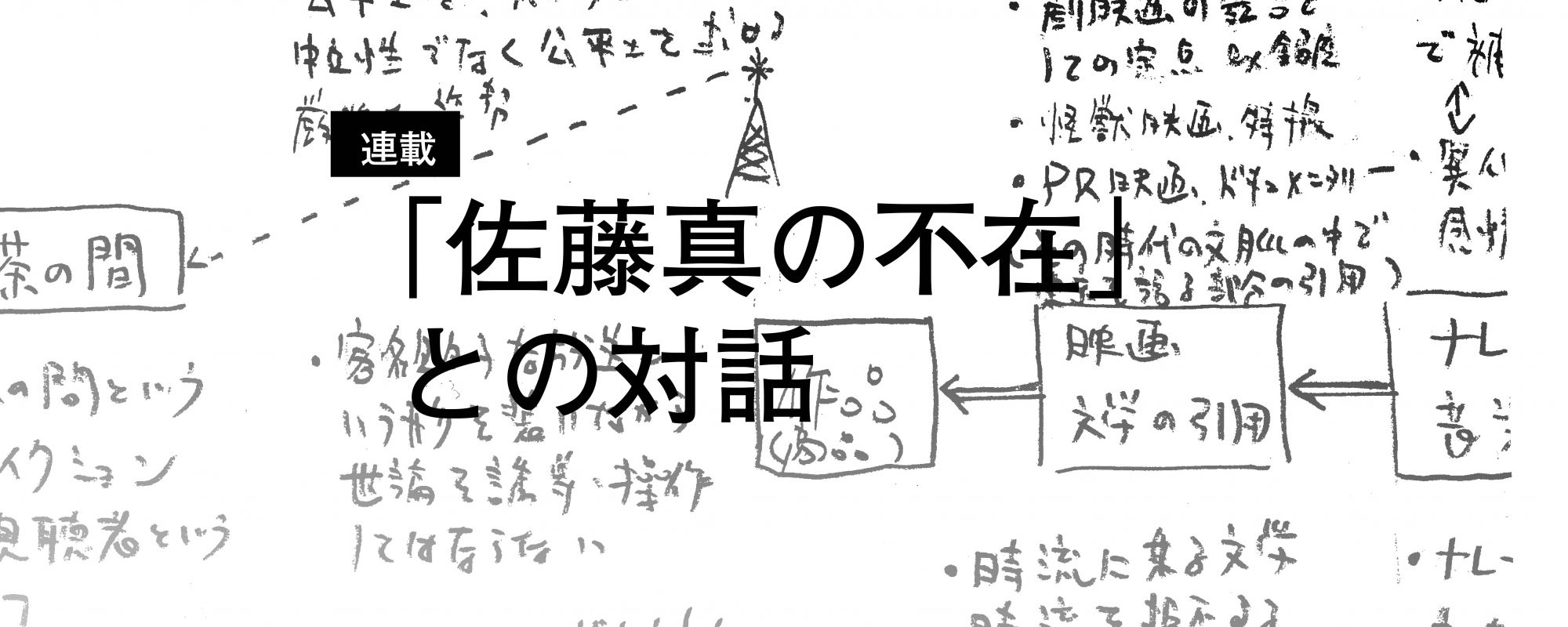第6回 後編
小林茂「わからないから撮る」
2019年9月22日 公開
「わからないから撮る」——佐藤真と小林茂の往復書簡
山本 里山社の『日常と不在を見つめて』には、佐藤さんと小林さんが交わされた往復書簡が収録されています。この手紙は佐藤さんが亡くなるどれくらい前のことだったんですか。
小林 最後の手紙は2007年の2月ですね。その年の9月に佐藤さんは亡くなりました。
山本 佐藤さんは僕にとって、映画監督として世間的な評価もあって、ドキュメンタリーの本もたくさん書かれていて、知的で、かつ実践もしている巨人だったんです。怖い人というイメージで。そんな人が小林さんに、どう表現したらいいかわからないんですが、つらいとか、自分がなぜ、映画を作っているのかという率直な悩みを手紙で打ち明けていることに驚いたんです。
この手紙が交わされた当時、小林さんはケニアで『チョコラ!』という映画を作っていて、佐藤さんはパレスチナで『エドワード・サイード OUT OF PLACE』という映画を作った後だった。佐藤さん自身はなぜ自分が縁もゆかりもないパレスチナで映画を作っているのかということに自問自答していて、小林さんにも、なぜあなたがケニアで映画を作っているのかを問うことが、次の映画の勝負どころになるんじゃないかと手紙に書かれている。『阿賀に生きる』という映画で小林さんは、まだ何もわかっていなかった青年が一人の映画監督になっていく時間を一緒に過ごされました。小林さんが佐藤さんのもっとも傍にいた人だと思うんですが、作り手として、ドキュメンタリストとして、なぜ自分がそれをやるのかっていうのは、やっぱり昔から佐藤さんと小林さんの間でもいつも話されていたんですか?
小林 そうですね。少し答えとは違うかもしれませんが、若くして、勝算もなく飛び込んでいった『阿賀に生きる』という映画が佐藤さんの礎なんです。だからそこを土台にして、佐藤さんはいろいろな形の家を建てていったと思うんです。でもその後は依頼もくる。
山本 プロデューサーが佐藤真にこういうの作らせたいとか。
小林 はい。だからそういう意味で言うと、自分が本当に作りたい映画を作っていくことの難しさ、困難さはあったと思う。過ぎてしまったあの『阿賀に生きる』の3年間がね、キラキラと、星のごとく光って見えていたんじゃないかと思うのね。それが佐藤さんの矜持だと思うし、そしてたとえ依頼された映画でも、自分の土台にして、自分なりに家を建てる。柳澤監督の影響も、僕を通してだけれども、佐藤さんには結構あったと思うのね。そういう話も結構してたし。僕はよく柳澤監督から、こうすればああなるっていうような、映画を作るときの技術的な引き出しを使い始めたら、もう終わりだぞってよく言われてたのね。
山本 ああ。手札手管というか。
小林 そういう映画って嫌らしいのね。こうやって涙腺を引っ張ると涙が出る、というような。そういう映画を作りはじめたらもう駄目だよと。僕なんかは福祉の映画を作ってるから、そういう福祉映画を涙流して観ながら、「こういう映画つくっちゃ駄目だよな」と思うんだよね。佐藤さんは、いつも苦しんで苦しんで、あの原点に戻って、これはどういうふうに作ったらいいか、引き出しから出さずに考えて作った。だから一作一作違うでしょう。
山本 違いますね、明らかにスタイルが変わっていきますね。
小林 僕は手紙の往復でも、佐藤さんは一作一作、引き出しを開けずに苦しみながら、でも新しいチャレンジを繰り返してきたじゃないかと伝えたんです。そのことを僕は認めるし、それが佐藤さんのいちばんいいところだから、こういうときは少し休んで、またやろうというような手紙を書いた。佐藤さんのほうからは「ケニアにいるコバさんを見てると現場が懐かしい」と。今でも飛んで行きたいというような手紙が来た。佐藤さんはその頃、有名になって、日本のドキュメンタリストを代表するような形で、世界中の映画祭の審査員とか、日本のドキュメンタリー特集みたいな場所に呼ばれていたんだけど、それについて「恥ずかしい限りだ」というようなことを書いてる。でもまさに日本のドキュメンタリーの過去も行く末も踏まえた上で、佐藤さんは「日常」という言葉とか、そういうものを定着していった張本人だと思うんです。そういうことを考えたら、佐藤さんが呼ばれるのは当たり前の話なんだけど。
僕は言ったんです。「書いたことが全部自分に返ってくるのはわかるよね」と。佐藤さんは、それはわかると言ってた。だから映画を作りながらあれだけの本を書くっていうことの覚悟は、相当なものだったと思うね。僕はそれについては、心配した。ただ、自分の足跡を、映画だけじゃなくて文章としても残せる人だったし、それから残しておくべきだと、どこかで思ったところがあると思うのね。
最初は『阿賀に生きる』だった。そこからいろんなものを見ていく中で、佐藤さんはいわゆる教条主義にはまっていくことの恐ろしさを感じていた。そして最初から結論に導こうとする、そういう人たちがつくるドキュメンタリーを否定していきたいわけです。つまり、わからないから撮るんだっていうこと。撮るたびにわからなくなっていくという、そのプロセスがなくて何のドキュメンタリーだというのが、彼の言い分だし、僕もそう思ってるけど、そういう段階だったと思うのね。この本にある佐藤さんの手紙にも夏目漱石のことが出てくるけど、夏目漱石が49歳で亡くなり、坂口安吾も49歳でした。
山本 2回も書いてありましたね。
小林 夏目漱石も、神経症みたいなところもあっただろうし、だからそういう意味で言えば、夏目漱石と比べるのはおかしいかもしれないけれど、佐藤さんは、普通の人で言えば人生三つ分ぐらいの仕事をしたんじゃないかと、今は思うね。
山本 小林さんの『風の波紋』は、新潟の十日町の、過疎の村を撮ったドキュメンタリーですよね。その村に都会や違う地域から移住した人たちの映画を、これもまた長い時間を掛けて作られた。やっぱり『阿賀に生きる』があっての『風の波紋』っていうのは、小林さんの中ではあるんですか。
小林 そうですね。『阿賀に生きる』は僕にとって、嫌で逃げ出してきた新潟という地に、もう一度30歳過ぎて出会い直させてくれた映画なんです。
山本 その後はご自分で映画を監督するようになられましたね。
小林 僕は佐藤さんが亡くなられてから鬱になるんです。9月4日の命日が近付くと駄目で、具合が悪くなるのを繰り返しました。僕は透析を受けるようになって10年ですが、ちょうどケニアへ行った後にすぐ透析になりました。それから更に鬱になって、鬱っていうのはこんな苦しいもんかと、佐藤さんの気持ちもわかる気がした。そしてクリニックに通ったりしていたんですが、あるとき新潟の十日町に移住してる友人のところに行ったんです。そしたらみんな歓迎してくれてね。でも農業者だから、夏はみんな朝4時ぐらいにいなくなるのね。僕が6時ぐらいに起きると誰もいない。昨日の夜のことが、キツネに包まれたような感じでね。山を見ると夜露が草にくっついていて、それがまぶしい夏の光に光ってるのね。山が光ってた。それを見たときに、ああ、ここなら映画ができるんじゃないかなと思った。結局その後7年ぐらい掛かってるんだけども。

『風の波紋』より(C)カサマフィルム
佐藤さんとはその後、秩父をずっと回っていた時期があって、秩父の映画を撮ろうとしてたんです(詳細は『日常と不在を見つめて』内、「往復書簡 佐藤真・小林茂」をご参照ください)。そのとき一緒に回ってくれた大野和興さんという農業ジャーナリストが、「日本を大木に例えたら、最終的には毛細根みたいなところから栄養を吸収していくもんだ」と。「毛細根が駄目になればどんな大木でも倒れる。小さな山村の一つ一つが毛細根に当たるのではないか」というふうに大野さんは言ったんです。僕は長年映画を作ってきて、それは本当に大事なことだと思った。山が駄目になれば中流域、下流域、海とみんな駄目になっていく。広島で、山崩れで川に土砂が流れる映像がニュースで流れていましたが(平成26年8.20広島市豪雨土砂災害)。
山本 ありましたね。
小林 土砂災害で魚が浮かんでたの、見ましたか? あれ、不思議でしょう。魚はエラ呼吸してるから、そこに細かい泥が入ったときに呼吸ができなくなって浮くんですよ。それと同じように、福島の原発事故後、阿武隈川にすごい量の放射能が集まるわけね。怖いのは食物連鎖で濃縮していくわけです。水俣と一緒だよね。チッソだって、海に流れて薄まればいいだろうと思ってたわけ。ところが生物界っていうのは全部食物連鎖で濃縮していって、そのピークのやつを人間が食うわけです。そうなるには何年も掛かる。だから自分たちが自然のサイクルの中で生きてるんだということを、この映画では表現をしているんです。豪雪地帯で、本当に一人じゃ生きられないんだよね。ある人が、豪雪のときに、お互いが助け合うなんてのは、ごく当たり前でね。それはここに生きてきた人間のDNAだと言ったんですよ。そういう意味で、ここには人間の原点がある。私が『風の波紋』のために書き下ろしました『雪国の幻灯会へようこそ』という本に、そういう話や、ドキュメンタリー映画を撮った半生記や、佐藤さんについてのことも書いてあります。是非読んでみてください。
山本 最後に、小林さんが今後考えている作品はありますか?
小林 あることから、性暴力に遭った被害者の人たちと出会ったんです。性暴力っていうのは「魂の殺人」と言われるらしいんですよね。それは男社会の問題でもあるわけです。女を支配したいという欲求、そのことと同一らしいのね。僕が映画を作ろうとしている女性は、被害に遭った後、「世の中から色がなくなった」って言うのよ。そしてある本屋で写真集を見たときに、「ここだったら私は生きられる」っていうことで写真を始めたらしい。その人のドキュメンタリーを撮っています。僕も鬱になったり、精神的なことでは負けないから(笑)、興味を持って。
山本 負けない(笑)。
小林 生き残り者ですよ。佐藤さんの『SELF AND OTHERS』がいい例だけども、映画は本当にドキュメンタリー的な、人間の内奥をつかみ出すような映画ができないかなと、今5、6年思っているんだけどね。『SELF AND OTHERS』で牛腸さんの生前録音されていた声がさ、「あいうえお、聞こえますか、聞こえますか」って流れるじゃない。あれ聞いた途端に、あの映画全部ひっくり返るじゃない。僕は恐れを感じたよね。
山本 もう怖いですよね。
小林 怖いですよ。そういう世界を佐藤真は切り拓いてきた。僕も自分のこれまでやってこなかった引き出しを開けることをしていきたいですね。
山本 「わからないから撮る」っていうこと、今も続けてらっしゃるわけですね。
小林 そうですね。それを続けていきたいなと思っています。
【上映情報】
山形国際ドキュメンタリー映画祭
YIDFFネットワーク特別上映「やまがたと映画」
10月12日(土)
小林茂の師、柳澤寿男と、弟子、小林茂。師弟2人がそれぞれ40年の歳月を隔て、同じびわこ学園を舞台に描いた2作品を上映する。
会場:山形まなび館
12時半〜 柳澤寿男監督『夜明け前の子どもたち』上映
15時〜 小林茂監督『わたしの季節』上映(佐藤真編集作品)
17時〜 トークショー(小林茂監督ほか)
入場無料
10月24日(木)
グローイングアップ映画祭 鶴川ショートムービーコンテスト2019プレイベント映画上映会『阿賀に生きる』
会場:和光大学ポプリホール鶴川 B2Fホール
17時半開場
18時開演
映画上映後トークイベントあり
一般:1,000円
中学生以下:500円
詳細はこちらまで。
(つづく)