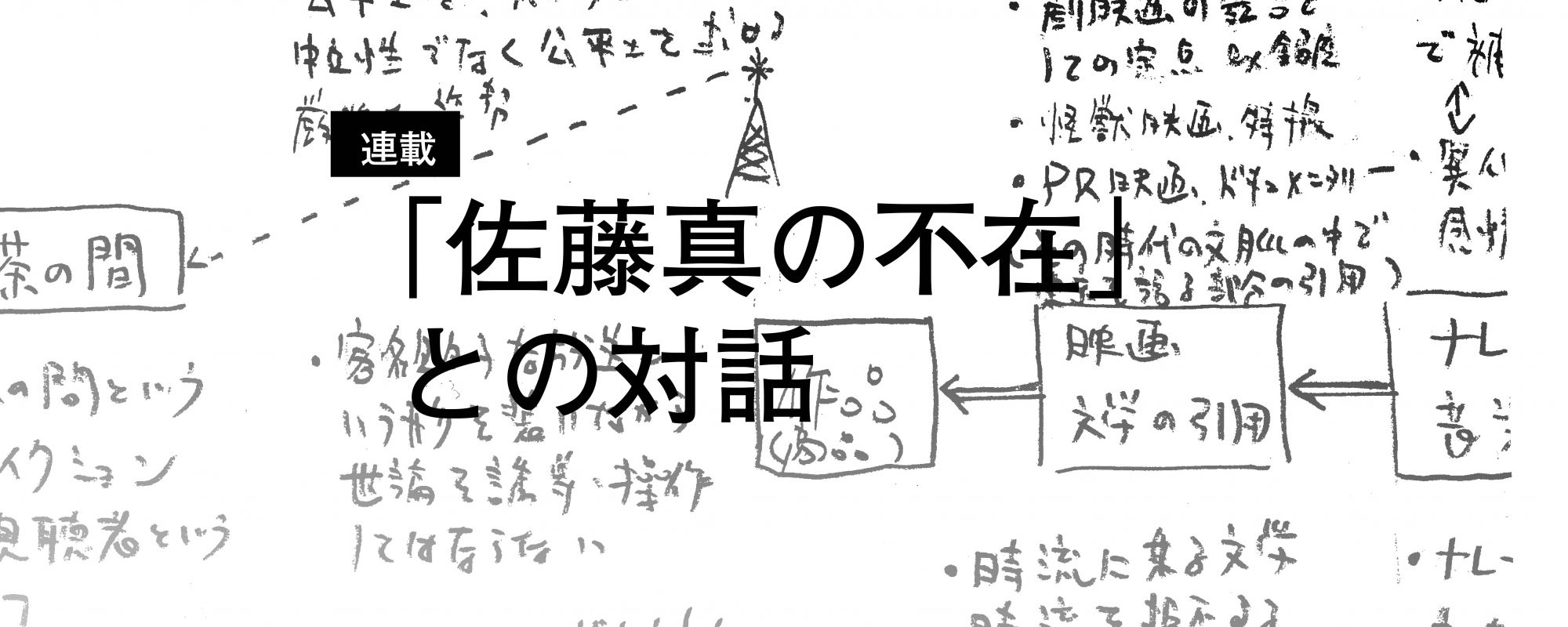第2回 後編
赤坂憲雄×旗野秀人×小森はるか「福島に生きる」は可能か。
2018年11月16日 公開
2016年3月、書籍『日常と不在を見つめて ドキュメンタリー映画作家 佐藤真の哲学』の刊行とともに始まった東京・御茶ノ水のアテネ・フランセ文化センターでの佐藤真の作品上映とゲストによる対談は大盛況となり、神戸、京都、福岡、福島、横浜へと、上映の波は広がっていった。この対談連載は、本上映会でのトークを再構成したものである。
佐藤真の「不在」が、いかにその「存在」を濃くし、不在に向き合うことが、いかに私たちの考えを深めていくものなのか。そして彼が目指したものが、私たちが理性を持って現代を生きぬいていくためにいかに必要な姿勢か。本連載は、不在の佐藤と、いまの時代に佐藤真の視線を持ち続ける人々との対話である。
今回は「福島に生きる」(前編)に続き(後編)をお送りします。
「生きてて良かった」と思ってもらいたくて始めた「冥土のみやげ」運動
小森 旗野さんが『阿賀に生きる』が出来上がった後もずっと続けていらっしゃる「冥土のみやげ」という団体の活動は、まさに傷つけられてしまったものをなんとか繋ぎとめていくようなものだったのではないかと思います。どんなことをされているかお話を伺ってもよろしいですか?
旗野 私自身も裁判が始まると、ついつい「この人には認定になってほしいから、できれば1000万円あげてほしい」という気持ちになる。だけど村には、魚を獲ったら隣の家におすそ分けしてダイコンをお返しにもらったりするような、貧しいながらもお互い様精神というのが成り立っていたんです。ところが、水俣病の裁判闘争をすることで「あのじいちゃん、草取りしたりしてあんなに元気そうなのに、裁判やって金持ちになって1000万円もらったんだって」といったふうに、症状の辛さもさることながら、仲が良かった隣近所の関係がズタズタになる。みんなそのことのほうが辛い。
裁判は、82年から13年半くらい続きます。そして95年12月、いわゆる政治決着ということで苦渋の選択をして和解してしまうんです。納得してるわけじゃないけど、患者さんたちが高齢でどんどん亡くなっていって、死んでしまったらおしまいだということで、不思議な金額なんですが、260万円という現金と、医療手帳を交付するということで裁判を終わらせてしまうんです。
すると患者さんたちは「やっと裁判が終わった」と喜んでるわけですよ。「何したい?」って聞いたら、「温泉に行きたい」って。「そんな簡単なことを我慢してきたの?」って聞いたら、周りの人から「裁判やってるくせ」にとか「ニセ患者のくせに」とか「カンパで温泉行ったんじゃないか」とか言われるからずっと我慢してきたっていうんです。それじゃあすぐに行こうってことで、95年12月に患者の会の人全員で温泉に行きました。
みんな喜んで、温泉にいっぱい入って、カラオケ歌って。次の日の朝、「旗野さんありがとね。冥土のみやげ出来たわね」って改めて感謝された時に、20年あまり付き合ってるのに、俺はこんな単純な願いに気づかなかったのかということにショックを受けた。だけど、これからでも遅くない。残った人たちに「水俣病にはなってしまったけど、生きてて良かった」っていう冥土のみやげをいっぱいつくる楽しい運動やってもいいんじゃなかろうか。今後も裁判を続ける人もいるんだけども、俺はこの人たちとずっと寄り添って、とにかく生きてて良かったって思ってもらえるような活動をできたらいいなと思ったんです。
それから、花見とか温泉とか、“ころり三観音”めぐりっていう「会津の三観音を巡るところりと逝ける」っていうお参りに行ったり。でも三回行ったらころりといく患者も本当にいたりして。それで毎年、五月四日に「追悼集会」って言いながら『阿賀に生きる』を観て、ゲストを呼んで、その後温泉旅館で宴会をするっていうことを続けてきました。そしたらだんだん『あがの岸辺にて』を今回朗読してくれたチカちゃん(小林知華子さん)みたいに若い人がどんどん参加してくれるようになったんです。
みんなあの映画のファンでいてくれるし、もっと言えば餅屋の加藤のじいちゃんを好きな人、遠藤さんを好きな人、芳男さんを好きな人、そういう人たちが集まって、映画の世界がずっと続いている気がするんです。水俣病の問題を越えた人の縁が繋がっていく。そういうものは、福島の原発事故にもやっぱり繋がるんじゃないかなって。事故や事件というのは、いっときですぐに忘れる。だけど、人の縁というのはそうじゃない。みんなに「死ぬまで付き合ってね」って言われたけど、死んでから25年経っても追悼集会やって、うまい酒飲んでる。こんなの本当にバチ当たりなんだけども、でも実はとても大事なことなんじゃないかなって。ちょっと余計なことまでしゃべったね。もう終わりでもいいくらい(笑)。
小森 いえいえ、まだお時間あります(笑)。映画に出ている方達が亡くなられても、佐藤真監督が亡くなられても、いろんな地域での上映も続いてますし、何よりも映画が生まれたその場所で映画が根付いている。この土地にこそ必要な映画として見続けられています。ところが世界中を飛び回ったこの映画が、阿賀野川流域では、地元ではやはり水俣病を言ってほしくないということで、長いあいだ上映が難しかったと伺いました。それが2015年から「阿賀野川遡上計画」というプロジェクトで阿賀野川沿いの公民館などを借りて上映する計画を、これも阿賀野川の河口、松浜で生まれた私と同世代の平岩史行さんが発起人になって実行されました。こういう映画のあり方は、私自身、作り手として本当に希望です。
『福島に生きる』は可能か
小森 『日常と不在を見つめて』の本に書かれている赤坂さんの文章で、私がいちばん自分に突きつけられていると感じたのは、「この見えない世界を、映像はいかにして映しとるのか。わたしには答えがない。しかしそこにこそ、『福島に生きる』が生まれなければならない必然が見え隠れしているのだ、と信じてみたい」という部分でした。『阿賀に生きる』はその地域にスタッフの人たちも住み込んで、患者さんたちもその地を離れずに暮らし続けるということができたから作られた映画でもあったと思います。そんななかで、『福島に生きる』は可能なのか。まず放射能という、カメラにも写らない、写すことができない問題、その土地に行ってもそこで暮らすおじいちゃんおばあちゃんには会えないかもしれないという状況の中で、『福島に生きる』を撮るということについて、私はずっと引っかかっていました。いまの福島をずっと見続けていらっしゃるお立場として、赤坂さんはこのことについてどう思われているのか、この場でお聞きできたらと思います。
赤坂 この文章を書いたときは、新潟水俣病と福島の原発事故の影響を重ね合わせられるかどうかを考えていたんですが、いまの時点では、やはり随分違いますね。まず有機水銀が侵すのは自然の中の川だけです。だからその魚を食べた人たちに障害が出るわけだけど、放射能汚染は、僕は“山野河海”という言葉をずっと使ってますけども、つまり人間たちは、山や野や川や海をいろんな形で利用させていただきながら、農というものを成り立たせている。その山野河海がまるごと汚染されてしまっている地域というのは、有機水銀による被害とは相当レベルが違います。だから、家屋敷の周りを除染して、さあ住んでくださいと言われても、その背後に広がっている山野河海は、もう除染なんかできないで取り残されてしまっている。昔の生活になんて戻れやしない。だって、キノコも山菜も食べることができない。山野にいるものたちを狩猟という形で捕っていた人たちが、どんどん狩猟免許を返しているというのは、殺しても食べることができないということです。我々が体験したことのないレベルの災害、しかも人間が作り出してしまった巨大な災害の中に巻き込まれているということを前提に考えざるを得ない。
もうひとつは、難民、棄民が生まれているということです。人が住めなくなっている。水俣病の場合は難民になったり棄民になったりしているわけではなく、人間は傷ついた自然の傍にとどまって、なんとか暮らしや生業をつないでいくことができる。やはりそこも違います。そして、この映画は佐藤真さんら若者たちが7人、農作業を手伝いながら、住み込みで食わせてもらいながら作った映画です。そういうことができる環境は今の福島にはない。福島には特有の困難があるなと感じています。

『阿賀に生きる』は住み込みで撮影した。右端が佐藤真、後列右が小林茂。(撮影:村井勇)
でもね、いっぽうで、水俣病も目に見えるものじゃなくて、この映画全体を見ることによって初めて見えてくるものがある。曲がった指のシーンばかり集めれば新潟水俣病が見えてくるのかと言ったらとんでもないことで、そういう意味では新潟水俣病だって見えない現実、見えない出来事だからこそ、こういう映画が成り立ったんだと思います。
そういう意味では福島だって、見えない現実を写し出すのが映画や芸術なのかもしれない。だから見えないということに絶望して、ここに今起きていることは表現できない、と言ってしまうのはきっと違うんだよね。きっと違うんだということに少しずつ気づきながら、でも僕は時間がかかると思う。福島は、まだ5年と8ヶ月なんですよね。それを表現に定着して、人々が落ち着いてそれを受け止める余裕はまだない。
2015年にノーベル文学賞を取った『チェルノブイリの祈り』は、著者は現場で死にいく人たちの惨憺たる状況を聞き書きしながら、それを表現の媒体に載せることができずに、あがいてあがいて15年くらいかかってようやく表現できるようになったそうです。起きてしまったことが途方もない出来事で、それを定型的な表現や定型的な言葉の織物の中に取り込むなんて、たぶんできない。だからきっと時間がかかる。でも、それをきちんと文学や映画といった表現の中に表していく仕事は絶対に大切です。佐藤真さんの『阿賀に生きる』という映画があったことによって、僕らは対話したり、いろんなことができている。
震災の後、言葉が溶けていってしまいました。政治の言葉、経済の言葉、科学の言葉が実にいい加減で我々をごまかしてばかりいる。だから、文学の言葉や芸術の言葉、映像の言葉、そういう言葉こそが我々を深いところで、長い時間かけて支えていってくれるんじゃないかと改めて感じるようになったし、少しずつそういう言葉が、表現が、生まれてきています。それを支えたり、育てたりすることが必要なんじゃないかなと思って、僕は柄にもなくいま、アートに深く関わるようになっています。
小森 「時間がかかる」というのは『阿賀に生きる』そのものも教えてくれていることです。水俣病の公式発表があってから24年経った後に佐藤さんたちも阿賀に住み始めました。今更新潟に行っても何も映らないし、遅いという話をされながらも、旗野さんは「このおじいちゃんおばあちゃんたちをそのまま撮ってくれたらそれでいいんだ」と説得して、佐藤真さん自身もそういう気持ちがあって、あの場所に表現が生まれました。水俣病の発生からだいぶ時間が経ってからこの映画が出来たということもとても大事なことだと思います。