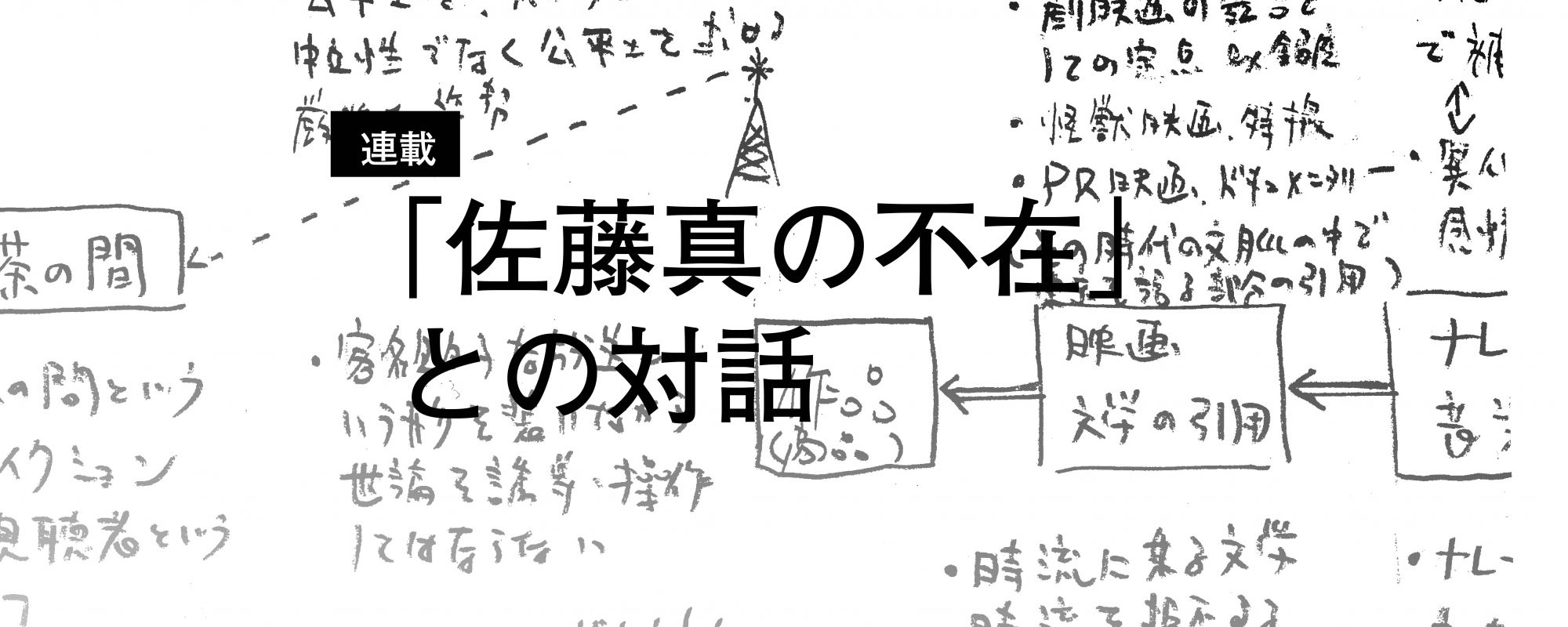第6回 後編
小林茂「わからないから撮る」
2019年9月22日 公開
2016年3月、書籍『日常と不在を見つめて ドキュメンタリー映画作家 佐藤真の哲学』の刊行とともに始まった東京・御茶ノ水のアテネ・フランセ文化センターでの佐藤真の作品上映とゲストによる対談は大盛況となり、神戸、京都、福岡、福島、横浜へと、上映の波は広がっていった。この対談連載は、本上映会でのトークを再構成したものである。
佐藤真の「不在」が、いかにその「存在」を濃くし、不在に向き合うことが、いかに私たちの考えを深めていくものなのか。そして彼が目指したものが、私たちが理性を持って現代を生きぬいていくためにいかに必要な姿勢か。本連載は、不在の佐藤と、いまの時代に佐藤真の視線を持ち続ける人々との対話である。
***
『阿賀に生きる』、そして10年後の阿賀を撮った『阿賀の記憶』のカメラマンであり、現在は『風の波紋』などで知られる映画監督の小林茂さん。3年間、阿賀の地に移り住んだ撮影では、佐藤と熱い議論を戦わせる日々の中、学びながら映画を作り上げた。疎遠になった時期を経て、佐藤が晩年、盟友、小林さんに宛てた手紙(『日常と不在を見つめて』の書籍の中に収録)は、互いに病を得た後、「わからないから撮る」という、二人の原点を確かめ合い、励まし合う内容だった。今なお映画に向き合い続ける小林茂さんが、当時を振り返りながら、今改めて佐藤真について思うこととは。佐藤真の助監督として、佐藤の仕事を仰ぎ見ていた、映画監督で映像ディレクターの山本草介さんが聞き手を務める。前編に続き、後編をお届けする。
大人になった二人が撮った、10年後の『阿賀の記憶』
小林 『阿賀に生きる』から10年後を撮った『阿賀の記憶』は僕が脳梗塞で倒れて撮影が延期になって、再び撮影し始めるんだけど、カメラを回せる喜びに満ちている作品なんです。
山本 『阿賀に生きる』のときみたいなケンカはもうないんですか。
小林 10年経って、『阿賀の記憶』を作りたいという話になって、佐藤さんから長い手紙が来たのよ。その手紙があれば本当は、この本(『日常と不在を見つめて』)の中に入れてくれたと思うんだけど、僕があんまり大事にして持ち歩いたもんだから、見つからなくなっちゃって(笑)。
山本 持ち歩いたんですか。
小林 そう。その手紙には、『SELF AND OTHERS』のキャメラマンの田村正毅さんに頼んだら断られたって書いてあるんですよ。僕に頼むのに、普通言わないでしょ。田村さんから、「佐藤さん、頼むキャメラマンが違うんじゃないかい」と言われたらしいんです。
山本 ははは。誰とは言わないけど。
小林 もう一回小林とやりなさいということでしょ。でもそれを読んだときに、これを断ったら、俺という人生はなんなんだというふうに感じたのね。僕は、佐藤さんとやることはもうないなと、諦めてたわけですよ。そういうところに手紙が来たから、是非やらせてくださいと返事をした。
山本 『阿賀の記憶』の撮影に入る直前に小林さんが倒れられるんですよね。佐藤さんは、一回そういう経験したら世界が変わって見えるんじゃないかと言われたと?
小林 そうですね。
山本 実際そう感じられましたか?
小林 見える世界が違いました。佐藤さんは、新鮮に見える世界を切り取ってくれればそれだけでいいということを言ってくれた。佐藤さんもイギリスに留学して、映画草創期の頃の手回しの映写機の映像なんか見て帰ってきて、「小林さん、その映写機を止めることはできないか」なんて言ってきたり、昔のフィルムを剥いだら画がくっついたのを面白がって、スクリーンを吊って映写してそれを僕がフィルムで撮ったりして。『阿賀の記憶』のときは佐藤さんと非常にうまいこといきました。あんまり気持ちが良かったもんだから、僕はそのころ重症心身障害者のびわこ学園の人びとの映画を撮っていて、ふと、佐藤さんに、「もうすぐ、いま撮ってる映画が上がるんだけど編集してくれないか」って頼んだのね。そしたら「いいよ」ってすぐ引き受けてくれたんです。

『阿賀の記憶』より(C)カサマフィルム
山本 『わたしの季節』ですね。
小林 そうです。小林さん、ギャラはいいから、その代わりフィルムでやるのはすごく時間が掛かるから、一回全部テレシネにあげてと。
山本 デジタルにするということですね。
小林 週2日くらいはやれるからって言ってくれたんです。それで、佐藤さんと編集の秦岳志さんと二人して2カ月ぐらいで上げてくれた。佐藤さんは素晴らしいなと思ったね。
山本 さっき「世界が変わって見えるんじゃないか」って佐藤さんがおっしゃったことって、その後の作品にもつながっているんですかね?
小林 私は重症心身障害者の心象を撮るために倒れたんだと思った。神様が「お前一回こういう世界を経験してみろ」っていう感じでしょ。そうすると、自分が撮ろうとしていた姿勢がものすごく高かったっていうことがわかったんです。
山本 それは上から目線ということですか。
小林 そうです。彼らをどうしたらいいかっていう目線で見てるわけよね。僕が倒れたら医者と看護師がベッドサイドで「小林さんをどうするかねえ」と言ってるのと一緒でしょ。それを僕が聞いてたらなんと思う。
山本 めっちゃ嫌ですね。
小林 ストレッチャーでCTのところに運ばれていくときも、寝そべって上を見ながら蛍光灯が川のように流れていくわけです。そのとき「ああ、びわこ学園でストレッチャーに乗って移動してる子どもたちはこういう風景をいつも見てるんだ」と思って。これ頂きだなと思って。
山本 その状態の中で。
小林 左手は力が入らないんだけど、右手だけ鉄柵をつかむような力があるんです。引っ掛ければ16ミリのキャメラが持てる。だから片手でなんとかいけないかな、とかね。そういう場面が映画の中にも出てきますけど、僕が倒れなかったらあんなふうにはたぶんいかなかったし、福祉がどうのこうのって映画になったと思う。そうじゃなくて、彼らには人間が生きるってなんなんだっていう根本的なことで相対していけばいいと思った。彼らが「小林さん無理したらあかんで」っていう意味のことを「コバッダシデッ」って言うんだけど、なめらかな言葉で言われるよりも10倍くらい勇気付けられた。そう彼らから言われることの安堵感。そして、40年間にわたって徐々に障害が重くなることをわかりながら、そんな自分を受け入れてきた人間力。そういうものを撮ればいいんだと思ったわけでね。だから『阿賀の記憶』も、僕たちが過ごした場所だから思い入れはあるけれども、まばゆいばかりの川面を撮ればいいんだと。カニがいたらカニを撮ればいいんだと。
山本 『阿賀を生きる』を見た後に『阿賀の記憶』を見ると本当にびっくりしますから。まったく違うんですよね。あのころが懐かしいっていう映画でもないし。
小林 長谷川のばあちゃんが老人ホームに入ってたんだけど、内緒で助手さんにカメラ撮影してもらって、僕と佐藤さんとばあちゃんの3人で映ったのね。それで佐藤さんが亡くなったときにね、僕は、佐藤さんはあの映画の中に入っちゃったと思ったわけ。そして僕も入る場所があそこにあると思ってるわけ。
山本 いやいやいや。
小林 本当に。佐藤さんはあの中で生きてる。佐藤さんは映画の中にに入っていった。そういうふうに思うのね。