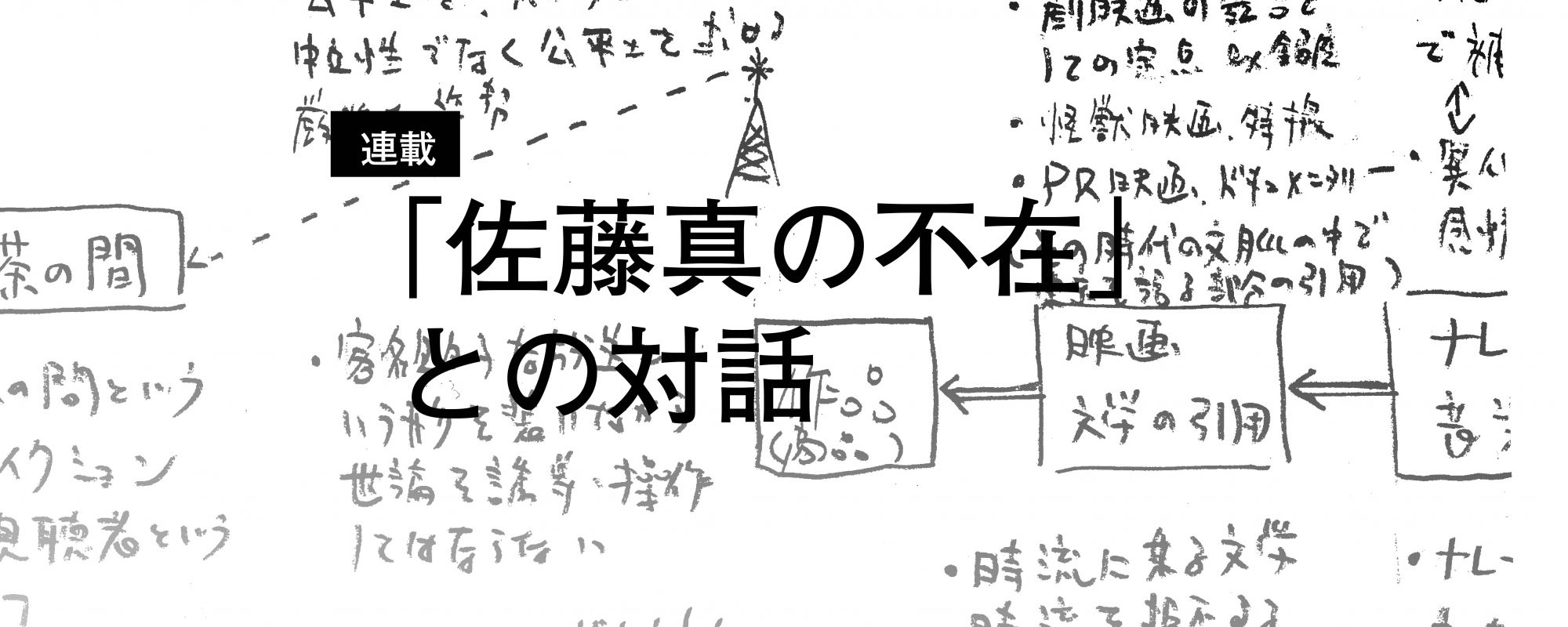第1回 前編
赤坂憲雄×旗野秀人×小森はるか「福島に生きる」は可能か。
2018年11月5日 公開
映画監督、佐藤真は2007年9月にこの世を去った。90年代から00年代にかけて作品を遺した佐藤は、政治の季節を過ぎた日本で、目の前の現実と向き合い「見えないものを見る」という粘り強い方法により、自分たちの時代の闇をあぶり出そうとしていた。
佐藤真は”日常“と”不在“を視点の基調とした。大事件や悲劇ではなく日常を、出来事が起きた後や、人物が居なくなった後の不在を撮る。それこそが、わかりやすい現実ではなく、現実の本質である「見えないもの」をあぶり出すように撮るための姿勢だった。
2016年3月、書籍『日常と不在を見つめて』の刊行とともに始まった東京・御茶ノ水のアテネ・フランセ文化センターでの佐藤真の作品上映とゲストによる対談は大盛況となり、神戸、京都、福岡、福島、横浜へと、上映の波は広がっていった。この対談連載は、本上映会でのトークを再構成したものである。
佐藤真の「不在」が、いかにその「存在」を濃くし、不在に向き合うことが、いかに私たちの考えを深めていくものなのか。そして彼が目指したものが、私たちが理性を持って現代を生きぬいていくためにいかに必要な姿勢か。本連載は、不在の佐藤と、いまの時代に佐藤真の視線を持ち続ける人々との対話である。
水俣病の運動からこぼれ落ちるじいちゃんばあちゃんの“宝もん話”
旗野 私は患者の会の活動を始めてから45年(※この対談は2016年秋に行われました)になります。出身は阿賀野川の河口から約30km、いわゆる中流地域と言われている安田町です。そこからまた30km上流に昭和電工がある。45年前の1971年、私は21歳の時に、東京のチッソ本社前で、ご本人も水俣病の患者で、未認定患者の会のリーダーだった川本輝夫さんが東京へ座り込みに来た時にたまたま出くわしたんです。新潟水俣病はその年の9月の判決で、ようやっと昭和電工が原因企業であるということが明らかになった。でも、71年の暮れに川本さんと初めて会った時、「9月の(新潟の)判決の後、どうなってる?」って言われて、まったく答えることができませんでした。最初の裁判では、安田町には患者さんはいないとされた農薬説だったんです。私も自分の町には患者もいないし、水俣病は他人事だと思っていたんですね。でもそのとき川本さんに「あんた、こんなところにいるよりも安田町に帰ったら? あんたのところにも必ず患者さんがいるはずだから、その手伝いをしたらどうだ」と言われた。
そしたら、安田に戻って翌年明けてすぐ、72年1月に、本当に偶然、安田町から認定患者が出たんです。だけど患者さんのもとを訪ねて話を聞こうにも「水俣の話なんてできない」と断られる。ところがその患者のばあちゃんは「水俣の話でなければ来ていいよ」というんです(笑)。それで訪ねたら、「じいちゃん(夫)は川舟の船頭なんだけども、水俣病の申請をしたのに棄却になった」と、向こうから話を始めてくれたんです。じいちゃんは市川栄作さんという方で、栄作さんも「おめさんも呑むかね?」なんてハナからそういう展開で、市川さんの長女が私の同級生だったりしたこともあって親しくなって「いや実は俺だけじゃねんだよ、家族も水俣病で。今度は船頭仲間みんなの話も聞いてくれ」ってどんどん思わぬ展開が広がっていきました。そしていわゆる“ニセ患者”、つまり補償金目当てじゃないかとか言われてなかなか申請できないとか、症状が足りないから棄却されたという認定基準の話といった現実的な話を聞くんです。そこで81年の二次訴訟の裁判まで、いわゆる未認定患者の運動をやりました。無我夢中で、精一杯「患者さんのために」と思ってやっていた最初の10年でした。
小森 いま手元に、81年に旗野さんが中心になって出された『あがの岸辺にて』という、未認定患者さんの聞き書き集があります。これはどういう経緯で作ることになったのでしょうか。
旗野 いい質問ですね(笑)。71年から10年間やっていたのは、行政不服の運動というものでした。たとえば、交通事故で片足を無くした場合は賠償金が10万円だけど、両足だと50万円になるというように、いかに水俣病による症状が揃っているか、大変かということを伝えて、少しでも多く患者さんに補償金が下りるようにする活動です。それはつまり、いかに悲惨な状態かを言えるかどうか、みたいなことなんです。ところが認定審査会ではお医者さんのカルテなんかを出してきて、「この人は症状がひとつだから水俣病ではない」とか「高度な学識と豊かな経験をもとにして、あなたは水俣病ではないと判断しました」みたいなことを言われる。それに反論するには、反論書というのを本人が書かなければならない。だから疫学的な裏付けを書いて欲しいんだけど、80過ぎのじいちゃんに「書いて」って言ったら、ずっと川の暮らしをしてきたじいちゃんは、震える手で好きな魚の名前を10匹くらいカタカナで書いたんです。それを見て私も「これじゃダメだよ。何歳からどれくらい魚食ったかって書かないと」みたいなことを言ったんです。でもその瞬間「あ、俺もいつの間にか行政と同じようなことをこの人たちに求めてるな」と気づいた。
「この人が80数年間、川筋に暮らして感じた精一杯の表現を受け取る余裕を俺はなくしている」と。患者さんは「生まれた時からここに住んでて、18になって嫁にいけって言われて、船に乗って嫁に来ました。そして初めて婿さんの顔をみたら船大工の遠藤さんでした」みたいに、延々と自分の一生を語る。その結果、120人くらいの組織の人たちが10年かかって一人だけ認定されましたが、ほとんど全員棄却されました。向こうが求める症状が揃わないんです。それで、さすがに82年に、「やっぱりこれは裁判しかないんじゃないか」ということになりました。

(C)「阿賀に生きる」製作委員会
でも、全然勝てなかった10年間で私は、この人たちには宝もん話があるということに気づくんです。水俣を見れば石牟礼道子さんとか、桑原史成とか、ユージン・スミスとか、土本典昭さんとか表現者がいっぱいいるのに、新潟は「四大公害裁判の先駆的な運動の勝利」みたいなことしか語られない。これはもったいないって思ったんです。
そこで、自分ができることは聞き書きかな、と、82年に仲間と一緒にガリ版刷りで聞き書き集を作るんです。それが長いあいだ絶版だったんだけど、実はこのあいだ(2016年)、35年ぶりに、若い人たちが「もったいない」って今風にして出しなおしてくれた。しかもその中の一人の、小林知華子さん、いつも「チカちゃん」って呼んでるんだけど、彼女のお母さんは、この中に出てくる上川村っていう阿賀野川の支流の出身で、本ができたときに二人で音読してくれたんです。それがすっごく嬉しくて。「俺がやりたかったのは、こういうことなんだな」って思った。