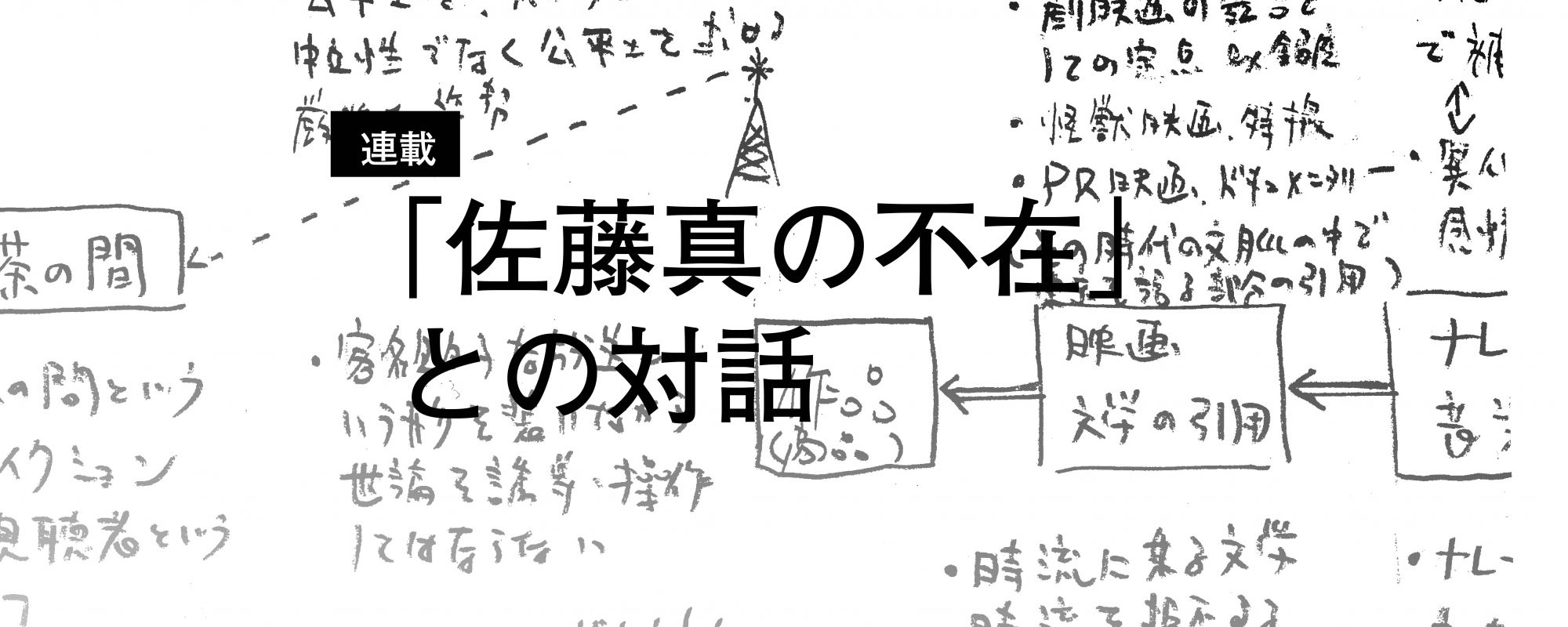第3回 前編
旗野秀人×永野三智「水俣病発生から【遅く来た若者】だからできること」
2018年12月7日 公開
生活者の視点でなければ水俣病問題の本質は見えない
—— 中学を卒業して水俣から出たいと思ったのは、「ここはもう嫌だ」というお気持ちだったんでしょうか。
永野 「こんなところ嫌だ」も含めて、いろんな事情が重なって、出ました。
旗野 私も新潟が嫌で一度出たから、同じだなあ(笑)。
永野 私の場合は旗野さんのようには考えずに、のらりくらりしながら過ごしていたんです。でもその後、子どもを産み、悶々としながら子育てしていた二十歳の時に衝撃的な出来事がふたつあるんです。ひとつは、障害者の人たちと出会ったこと。もうひとつは、2003年に溝口行政訴訟という裁判に出会ったことです。溝口秋生さんは実は、私の幼い頃からの書道の先生でした。この訴訟は溝口先生が原告一人で始めた裁判で、2001年に提訴して2013年に最高裁判決で勝訴をして終了します。03年の時点ですでに30年間、溝口先生はお母さんの認定を争っていました。溝口先生の息子さんは、実は胎児性水俣病患者でした。私は3歳から先生の家に通って書道を習いながら、まったく存在を知らなかったんです。私にとって、それまで溜めていたものがバーンと爆発したような感じでした。
その後、毎日挨拶を交わしていた近所のおばさんや幼馴染のお母さん、川本輝夫さんの奥さんもそうですが、ただ水俣に住んでいるだけだと思っていた、つまり水俣病とは関係がないと思っていた近所の人たちが水俣病を罹患していたり、闘っていたんだということを知り、衝撃を受けました。
そしてだんだんと障害者のことや水俣病のことを「学びたい」という欲が湧いてくるんですが、大学に行くのはちょっと違うという気持ちだった。子どももいるし、お金もない。当時はまだ「子どもが水俣出身になると、私と同じ思いをする。また逃げて暮らさなきゃいけない。子どもは水俣出身にはしない」という思いもありました。
そこで、子どもを連れて沖縄から障害者施設を転々とすることにしました。出会った人の家に親子でお世話になる生活でした。沖縄で出会った方々から聞く水俣の歴史はすっと頭に入ってきて、それは、私がそれまで持っていなかった水俣への「愛」みたいなものを積み上げていくような作業でした。そういう時期を経て、その後水俣に帰った理由のひとつは、子どもが「小学校に行きたい」「家が欲しい」って言い出したからなんです(笑)。
旗野 家なき子だ(笑)。
永野 子どもが5歳の誕生日に、「誕生日プレゼントはほんとの家が欲しい」って言うんです。私も実は精神的にも体力的にもボロ雑巾のように疲れ果てていて、最後に思いついたのが「もう絶対に帰らない」と思っていた水俣しかなかった。子どもには苦しい思いをさせたなと思います。
帰った当初は地域の大きな病院に勤めました。でも勤め始めて驚いたのは、検査技師さんとか看護師さんが、「水俣病患者がいるからこの町が暗くなる」と言うんです。「裁判をやっている人はすぐやめて欲しい。チッソが負けて補償金を払って潰れでもしたら、もう翌々週にはこの町の人口は半分になる。あれもこれもできなくなる。この病院もなくなる」「テレビに出る患者は恥ずかしい」なんていうことを言う人もいました。その病院は患者検診、つまり認定申請をする患者さんの検診をする病院なんです。それまで医療従事者は患者の味方だとばかり思っていたのに、まったくそうではない一面を見てしまった。そしてしばらくして、相思社に入りたいと思った時に、「相思社ってどんなとこですか」って病院の人に聞いたら、「ニセ患者製造所よ」って言われてびっくりしました(笑)。
相思社に入ったのは08年です。まだ裁判中だった溝口先生の暮らしを支えたいと思ったんです。私は裁判をする溝口先生が地域でも裁判所でも孤立しているように見えました。結局、いまだに先生には私が支えてもらえっているんですが(笑)。(※その後、溝口秋生さんは2017年9月12日に85歳で亡くなりました)
それと、自分のコンプレックスの根っこがなんであるかを知りたいと思いました。それまで水俣では、学校でも地域でも水俣病はタブーだという意識がありました。私自身が水俣出身であることを隠して暮らしていたので、相思社に入ると、水俣病についてごく普通に語る人たちの姿を見て、不思議な開放感がありました。そういえば、初めて裁判の傍聴に行った時もそういう開放感を味わったなと思います。
相思社に入ってからはずっと患者担当をしています。患者の方やその家族の差別が厳しかった頃のことや、近年、患者だと名乗りを上げた方の胸中を聞いたりしています。
—— 水俣市の学校では、水俣病について、たとえば広島の平和教育みたいな教育はないんですか?
永野 私の小学校時代は、先生から「あなたたちは水俣出身だっていうことでバカにされたりとかイジメられたりするかもしれないから、それに負けないように強くなりなさい」と言われました。
娘の同級生の親と何年か前、一緒に温泉に出かけたときに、靴を脱いだら白い靴下の先が真っ赤で、血が滲んでいるんです。「壁にぶつけたけど気がつかなかった」って。常に頭痛がするとか、震えがあるとか、そういう症状を持っている親たちの現在進行形の水俣病の隣で、子どもたちはどんなふうに水俣病を捉えているのかなと思います。
2年ぐらい前に県立水俣高校で講演の依頼をされたとき「できるだけ誇りを持たせる授業をしてください」と言われるんです。そこで、生徒たちに「水俣出身だって言える?」と聞いたら、400人中180人の生徒が「水俣出身だと言えない」って言うんです。ある女の子は「私は水俣が大好きです。自然も豊かで人も優しくて。だけど、水俣出身と言えない自分が大嫌いです」って。私が10代だった頃と、何も変わらないと思いました。
旗野 みっちゃん、あ、みっちゃんって言っちゃった。(「いいです」と永野さん)みっちゃんの話を聞きながらいいなぁと思ったのは、まずお母さんになってから水俣に関わったっていうことね。俺はそれがすごくいいことだなと思う。しかも、溝口さんのことを「書道の先生」って言うでしょ。あの当時、みんな和解してるのに唯一溝口さんは徹底抗戦で最高裁まで闘っていて、運動の切り口で捉えられてる人ですよ。その人をみっちゃんは「書道の先生」って、要するに生活者として患者である溝口さんと付き合ってる。そしてそのままのスタンスで相思社に入った。
ちょっと手前味噌ですけど、『阿賀に生きる』のなかに出てくる餅屋の加藤のジイちゃんに私は「そんなバカみたいな運動やるな。まずちゃんと大工として一人前になること。それから嫁さん連れて来い。でなきゃもう来るな」って言われたの。要するに生活者として自分が一人前になれたならまた来いって。世のため人のためみたいなことで、運動なんてやっちゃいけないんだとピシャッと言われたんですね。そういうことを、30歳になるまで誰も言ってくんなかった。加藤のジイちゃんは私にとって尊敬するおジイちゃんだから、すぐに嫁さん探しました。それですぐ結婚(笑)。ジイちゃんも喜んでくれて、私たちの結婚式とジイちゃんたちの金婚式を合同でやったの。そんで新婚旅行も一緒に連れてけとか言われて、6人くらいで新婚旅行に行きました(笑)。
とにかく「水俣病患者」という以前に生活者としての付き合いをして見えてくるもんじゃないと、何も見えなくなっちゃうんですよ。「患者」が先に邪魔して。だからみっちゃんも大変だったろうけども、やっぱりお母さんになって良かったし、そんなお父さんなんていなくても大丈夫なんです。ハッハッハ。
永野 (笑)。
(構成:里山社・清田麻衣子 / 構成協力:和島香太郎)
(後編)につづく
佐藤真(さとう・まこと)1957年、青森県生まれ。東京大学文学部哲学科卒業。大学在学中より水俣病被害者の支援活動に関わる。1981年、『無辜なる海』(監督:香取直孝)助監督として参加。1989年から新潟県阿賀野川流域の民家に住みこみながら撮影を始め、1992年、『阿賀に生きる』を完成。ニヨン国際ドキュメンタリー映画祭銀賞など、国内外で高い評価を受ける。以降、映画監督として数々の作品を発表。他に映画やテレビ作品の編集・構成、映画論の執筆など多方面に活躍。京都造形芸術大学教授、映画美学校主任講師として後進の指導にも尽力。2007年9月4日逝去。享年49。
影響を受けた人からともに歩んできた人まで、佐藤真に惹きつけられた32人の書き下ろし原稿とインタビュー、そして佐藤真の単行本未収録原稿を含む傑作選を収録。映像作家であり、90年代後半の類稀な思想家とも言うべき佐藤真の哲学を掘り下げ、今を「批判的に」見つめ、私たちの確かな未来への足場を探る。
第1章 阿賀と日常
赤坂憲雄(民俗学)、平田オリザ(演出家)、想田和弘(映画作家)、森まゆみ(文筆家)、佐藤丹路(妻)、小林茂(映画監督)●佐藤真と盟友・小林茂の往復書簡 ※佐藤真の手紙を初収録 ●座談会 旗野秀人(『阿賀に生きる』発起人)×香取直孝(映画監督)×小林茂×山上徹二郎(シグロ代表)
第2章 生活を撮る
松江哲明(映画監督)、森達也(映画監督・作家)、原一男(映画監督)、佐藤澪(長女)、佐藤萌(次女)
第3章 芸術
椹木野衣(美術評論家)、秦岳志(映画編集)第4章 写真と東京
飯沢耕太郎(写真評論家)、笹岡啓子(写真家)、諏訪敦彦(映画監督)●グラビア 佐藤真1990’s トウキョウ・スケッチ ※佐藤真の東京スナップが蘇る! 構成・解説:飯沢耕太郎
第5章 不在とサイード
四方田犬彦(批評家)、大倉宏(美術評論家)、八角聡仁(批評家)、ジャン・ユンカーマン(映画監督)●インタビュー 阿部マーク・ノーネス(映画研究)
第6章 ドキュメンタリー考
港千尋(写真家、映像人類学者)●企画書「ドキュメンタリー映画の哲学」
第7章 佐藤真の不在
林海象(映画監督)⚫︎論考「佐藤真をめぐる8章」萩野亮(映画批評)●インタビュー 小林三四郎(佐藤真いとこ、配給会社・太秦代表取締役社長)⚫︎教え子座談会 石田優子(映画監督)×奥谷洋一郎(映画監督)×山本草介(映画監督)●ルポ「佐藤真のその先へ−—−—「佐藤真の不在」を上演するということ」村川拓也『Evellet Ghost Lines』
(つづく)