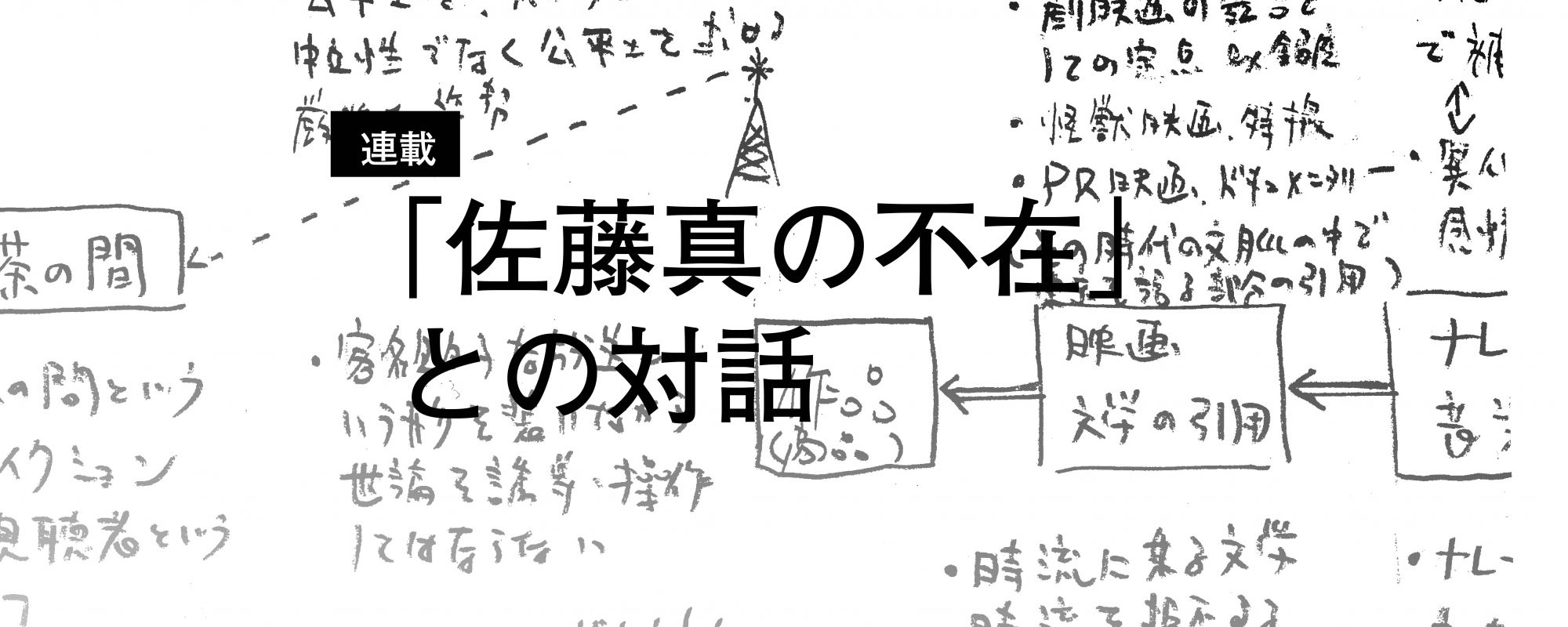第5回 前編
小林茂「わからないから撮る」
2019年9月15日 公開
2016年3月、書籍『日常と不在を見つめて ドキュメンタリー映画作家 佐藤真の哲学』の刊行とともに始まった東京・御茶ノ水のアテネ・フランセ文化センターでの佐藤真の作品上映とゲストによる対談は大盛況となり、神戸、京都、福岡、福島、横浜へと、上映の波は広がっていった。この対談連載は、本上映会でのトークを再構成したものである。
佐藤真の「不在」が、いかにその「存在」を濃くし、不在に向き合うことが、いかに私たちの考えを深めていくものなのか。そして彼が目指したものが、私たちが理性を持って現代を生きぬいていくためにいかに必要な姿勢か。本連載は、不在の佐藤と、いまの時代に佐藤真の視線を持ち続ける人々との対話である。
***
『阿賀に生きる』、そして10年後の阿賀を撮った『阿賀の記憶』のカメラマンであり、現在は『風の波紋』などで知られる映画監督の小林茂さん。3年間、阿賀の地に移り住んだ撮影では、佐藤と熱い議論を戦わせる日々の中、学びながら映画を作り上げた。疎遠になった時期を経て、佐藤が晩年、盟友、小林さんに宛てた手紙(『日常と不在を見つめて』の書籍の中に収録)は、互いに病を得た後、「わからないから撮る」という、二人の原点を確かめ合い、励まし合う内容だった。今なお映画に向き合い続ける小林茂さんが、当時を振り返りながら、今改めて佐藤真について思うこととは。佐藤真の助監督として、佐藤の仕事を仰ぎ見ていた、映画監督で映像ディレクターの山本草介さんが聞き手を務める。
素人集団だった『阿賀に生きる』スタッフ
山本 僕は佐藤真さんが青森県の八戸市美術館の依頼で子どもと一緒に撮ったアートフィルム『市場最大の作戦』(01年)や、『星の文人 野尻抱影』(02年)という教育映像を作った時期に、助監督として佐藤さんと一緒の時間を過ごしました。その辺りのことは『日常と不在を見つめて』の本に収録された座談会で話しをさせていただいております。そして今日のメインゲストが、こちらの『阿賀に生きる』のカメラマンで、映画監督の小林茂さんです。
小林 『阿賀に生きる』と、その10年後ぐらいの作品『阿賀の記憶』、また、佐藤さんの自主映画的なところでキャメラを回しております。今日この上映会で流した『阿賀に生きる』は、映画ができてから25年後に出来たデジタルリマスター版ですが、大変素晴らしい映像で、まるでフィルムを見ているような感じでした。デジタル化してもフィルムで撮ってる感じがよく出ていたと思います。
山本 『阿賀に生きる』は1988年からスタッフ宿舎「阿賀の家」を開設し、準備を進めて、翌年からクランクインして3年間かけて制作されました。当時監督経験のない佐藤真さんが、旗野秀人さんと出会ってこの映画が動き出したと思うんですが、制作の経緯を伺えますか。
小林 香取直孝監督の『無辜なる海 -1982年 水俣-』(82年)という作品は、スタッフ4人が水俣に移り住んで制作した映画ですが、佐藤さんは助監督でした。映画完成後、彼らはそれぞれ地域をわけて自主上映の旅に出て、新潟に行ったのが佐藤さんです。佐藤さんが新潟で出会った旗野秀人さんは新潟水俣病の患者さんの支援者ですが、来る人は皆受け入れる人で、酒を飲ませて泊まらせてくれた。旗野さんはその時佐藤さんに、「熊本の水俣病については、文学も映画も写真も演劇もある。実は阿賀野川のほうにも負けず劣らず川の豊かな世界があるんだが、表現されたものが少ない」と話した。他の人がみんな逃げるような話だったけど、佐藤さんだけは引っ掛かったわけです(笑)。しかし彼はこのとき、「映画監督になる」とは言ってないんですね。まずはとにかく『阿賀に生きる』を撮ろうということだけだった。そして、その後、正式に助監督の修行に入るんですよ。私はそのころ京都で水俣の支援活動をしていたので旗野さんはよく知っていました。『無辜なる海』のスタッフは知っていましたけど、佐藤さんとは会ったことがありませんでした。
佐藤さん曰く、「映画を撮るには家を一軒建てるぐらいのお金がいる。それからスタッフは3人いればいい。監督は自分がやる。あとは録音とカメラだ」と、そういうことで、録音は、映画を観た人にはナレーションで登場する、鍼灸の学校を卒業したばかりの新潟の鈴木彰二くんに、「鍼灸師もやるんだからマイクも持てるだろう」ということで録音部にしまして。撮影は、それまで私が写真集をいくつか出していたのを旗野さんがえらく気に入ってくれていて、「写真を撮るからには映画も撮れるだろう」ってことで、声がかかった。佐藤さんとは、新宿のションベン横丁(新宿西口思い出横丁の俗称)にある大黒屋っていう大衆酒場で、初めて会いました。二人とも酒飲みなんだけど金がないんですね。だからビールの大瓶1本とさんまの塩焼きで2時間。それで僕は断り続けていた。僕は柳澤壽男監督の助監督をしながら、スチールカメラマンもやっていたんです。でも映画のキャメラマンの経験はなかった。キャメラマンは大体10年ぐらい助手をしてからなるものなんで、最初は断っていたんです。
山本 佐藤さんは、どういう説得するんですか。
小林 要するにカメラを回してほしいってことなんですけど、僕は現場でキャメラマンがどれほど大変なのかを知ってるからずっと断っていたんです。でもある時、阿賀野川のほとりで集まりがあって僕も呼ばれました。そのとき、『阿賀に生きる』の冒頭で登場する舟大工の遠藤さんの家に連れていかれました。僕の生まれた家の傍にも川があって、幼いころ、隣のおじいさんが魚を獲りに行くときはどこでもバケツ持ってついて行きましたが、遠藤さんは、そのおじいさんと非常に似ていたんですね。映画の中で、遠藤さんのお茶の淹れ方がいいでしょう、ぽたぽたぽたぽたと丁寧に淹れる。僕は遠藤さんを見た時、こういう人を撮るんだったら映画を撮ってもいいんじゃないかなと思って、やるって決めたんですよね。

素人集団だった撮影スタッフ。左上が佐藤真、左上中央が小林茂。(撮影:村井勇)
山本 監督は初めての人で、カメラマンもスチールしか撮ったことがない人で、録音はなぜか鍼灸師がやってて。すごい組み合わせですよね(笑)。
小林 ド素人の集まりですよね。
山本 『阿賀に生きる』には、なんでこんなシーンが撮れるのかってシーンがいくつかありました。たとえば人の前で夫婦げんかをするとか、どうでもいいようなことだけど、そこにひき込まれていくんですよね。こういうのが撮れるのは、撮る側が素人だということと関係があるんですか。
小林 僕はニュープリントになってからも何回この映画を観たかわかりませんが、観始めると最後まで観ちゃうんですよね。昔は若い目線で見てたんですけど、だんだん自分自身が老人たちに年代が近くなってるので、今は若い人たちを受け入れるような目線で見ている。今は、この映画は若い映画だと思います。我々は、老人たちのお釈迦様の手の上で踊ってる孫悟空みたいなものだったんだなということがようやくわかります。ばあちゃんが「撮りなさんな」と言ったら、ひるむじゃないですか。それでも、僕らは回すでしょう。
山本 「カメラなんて回すもんでねえ」というところですね。
小林 そういうときに、「すいませんでした!」と言ったら、ばあちゃんは、がっかりするわけですよ。
山本 あ、そうなんですか?
小林 たぶん、がっかりするんです。それを無理に撮ってるから、しょうがないと思えるわけでしょ。たとえば今、若い人たちが僕のところに来て、「お前、俺のこと撮るなよ」なんて言って、「あ、すいません」って撮るのをやめたら、「なんだお前」ってなるでしょ。「すいません」とは言いながらもじわじわ寄ってくるとね、そしたら、「なかなかおぬし、やるな」となるわけです。